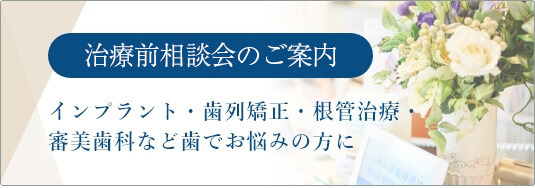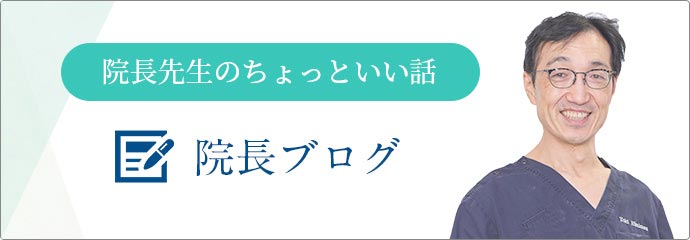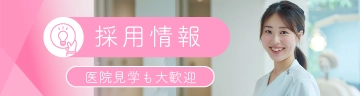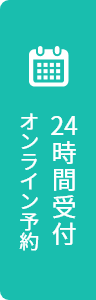歯茎に傷がついた原因と対処法|正しいケアで早く治すには?

歯茎に違和感…それ、傷かもしれません
「歯磨き中に歯茎から血が出た」「硬い食べ物で歯茎が切れた気がする」
そんな経験はありませんか?
歯茎はとても繊細な組織で、ちょっとした刺激でも傷つくことがあります。放置すると痛みや腫れ、感染につながることも。
この記事では、歯茎に傷がつく原因とその対処法、予防のポイントまでわかりやすく解説します。
原因①:日常生活で起こる歯茎の傷
歯茎に傷がつく原因は、意外と身近なところにあります。

- 歯ブラシの圧が強すぎる(オーバーブラッシング)
「しっかり磨かないと汚れが落ちない」と思い、力任せにゴシゴシ磨いていませんか?
実はこの“オーバーブラッシング”こそが、歯茎を傷つける最大の原因のひとつです。
強すぎる圧は、歯茎の表面を削り、炎症や後退(歯肉退縮)を引き起こすことがあります。
歯磨きは「やさしく・丁寧に」が基本。毛先が広がらない程度の力加減を意識しましょう。
せっかくブラッシングしているのに、逆に歯茎を傷つけてしまっています。小さな傷であっても、毎日の歯磨きで頻繁に傷がついてしまうのは歯肉にとって大きな負担となります。
- フロスや歯間ブラシの使い方が不適切
勢いよく挿入したり、無理に引き抜くと歯茎を切ってしまうことがあります。
- 硬い食べ物による刺激
せんべいや骨付き肉など、硬い食材が歯茎に当たって傷になることも。
- 無意識の癖
爪やペン先で口元を触る癖がある方は、歯茎を傷つけている可能性があります。
原因②:体質や口腔環境によるもの
- 歯並びの問題
歯が傾いていたり、被せ物が合っていないと、歯茎に慢性的な刺激が加わります。 - 口腔乾燥症(ドライマウス)
唾液が少ないと、粘膜が弱くなり傷つきやすくなります。 - 免疫力の低下
糖尿病や貧血などの持病やビタミン不足があると、傷の治りが遅くなったり、炎症が起きやすく、口内炎にもなります。
歯茎を傷つけない、正しいブラッシング圧を測る方法
歯磨きの力加減は、自分ではなかなか気づきにくいもの。以下の方法で、適切なブラッシング圧を確認してみましょう。
①歯ブラシの毛先が広がらない程度の力が理想
鏡を見ながら歯磨きをして、毛先が大きく広がっている場合は力が強すぎます。
毛先が歯と歯茎の境目に軽く当たる程度がベストです。
②キッチン用のはかりで圧力をチェック
歯ブラシをキッチンスケールに押し当ててみましょう。
理想的なブラッシング圧は約150g〜200g程度。
それ以上になると歯茎に負担がかかる可能性があります。
③ペンを持つような力加減を意識する
歯ブラシを握りしめるのではなく、ペンを持つように軽く持つことで、自然と力が入りすぎないようになります。
④電動歯ブラシの圧力センサーを活用
最近の電動歯ブラシには、強すぎる圧を感知して知らせてくれる機能がついているものもあります。
歯磨きの力加減に不安がある方は、こうしたツールの活用もおすすめです。

対処法:歯茎に傷がついたときのセルフケア
応急処置
- ぬるま湯や生理食塩水でやさしくうがい
殺菌効果があり、傷口を清潔に保てます。 - 出血がある場合はガーゼで軽く圧迫
清潔なガーゼで数分間押さえると止血できます。 - 市販の口腔用軟膏を使用
市販の口内炎の塗り薬を塗って、傷口を保護してあげるのも一つの方法です。悪化すると化膿し、歯茎の内側に膿が溜まる可能性もあります。痛みが強い場合には、歯科医院を受診しましょう。
歯茎の傷を悪化させないための注意点
- 辛い・熱い食べ物は避ける
- 歯磨きはやさしく、柔らかめの歯ブラシを使用
- フロスや歯間ブラシは一時中止、または慎重に使用
歯茎の傷が引き起こすリスクと、放置した場合の影響
小さな傷だからといって油断していると、思わぬトラブルにつながることがあります。
歯茎は非常にデリケートな組織。傷口から細菌が侵入すると、歯肉炎や歯周炎を引き起こす可能性があります。
特に口腔内は常に湿っていて細菌が繁殖しやすいため、傷があると炎症が長引きやすくなります。
繰り返し傷つけられた歯茎は、徐々に後退していきます。
歯の根元が露出すると、知覚過敏や虫歯のリスクが高まり、見た目にも影響します。
傷口が慢性的な炎症を起こすと、膿や出血が発生し、口臭の原因になることも。
また、食事や歯磨きのたびに痛みや違和感を感じるようになり、生活の質が低下します。
歯茎の傷を放置するとどうなる?
歯茎にできた小さな傷を「たいしたことない」と放置してしまうと、口腔内の細菌が入り込み、炎症が慢性化する恐れがあります。初期段階では軽い腫れや出血で済んでいたものが、やがて歯周病へと進行し、歯を支える骨(歯槽骨)が徐々に溶けていきます。
その結果、歯がグラついたり、最悪の場合は抜け落ちてしまうこともあります。
また、炎症が続くことで口臭や痛み、不快感が日常的に現れ、食事や会話にも支障をきたすようになります。治療が必要な状態になるまで気づかず、通院回数や治療費が増えるケースも少なくありません。
だからこそ、歯茎の傷は「早めのケア」が何より大切です。日々のブラッシング習慣を見直し、歯科での定期的なチェックを怠らないようにしましょう。
歯科受診の目安:こんなときは迷わず相談を
以下のような症状がある場合は、歯科医院での診察をおすすめします。
- 傷が1週間以上治らない
- 腫れや膿が出てきた
- 強い痛みや発熱を伴う
- 傷が繰り返しできる
これらは歯周病や口内炎、まれに口腔がんの初期症状である可能性もあります。
予防法:歯茎を守るためにできること
- 正しい歯磨き習慣を身につける
歯科医院でのブラッシング指導がおすすめです。 - 栄養バランスの取れた食事
ビタミンCや亜鉛は粘膜の修復に役立ちます。 - 定期的な歯科検診
歯石除去や口腔内のチェックで、傷の原因を早期に発見できます。
よくあるご質問
Q1歯茎の傷は自然に治りますか?
軽度の傷であれば、数日〜1週間ほどで自然に治癒します。ただし、痛みや腫れが続く場合は歯科医院での診察をおすすめします。
Q2歯茎の傷に市販薬を使っても大丈夫ですか?
口腔用の軟膏やうがい薬は一時的な対処に有効ですが、使用前に薬剤師や歯科医に相談するのが安心です。
Q3歯茎の傷が繰り返しできるのはなぜですか?
歯並びや被せ物の不具合、免疫力の低下などが原因の可能性があります。繰り返す場合は歯科医院での精査が必要です。
歯茎の傷は放置せず、やさしくケアを
歯茎の傷は、ちょっとした刺激でも起こりますが、正しいケアで早く治すことができます。
「いつもと違う」と感じたら、無理せず歯科医院に相談しましょう。
口腔内の健康は、全身の健康にもつながっています。
奈良県北葛城郡上牧町のかつらぎ歯科医院では、歯の治療だけでなく、歯ブラシの当て方や歯ブラシの選び方などもアドバイスしています。
オーバーブラッシングにならないような適度な力加減と正しい磨き方を身に付けて、お口の健康を維持しましょう。
分からないことや不安なことがあればお気軽にご相談ください!